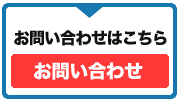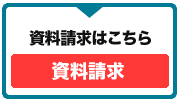写真:大塚(左)/西村氏(中)/藤本氏(右)
こんにちは、CSジャーナル編集長の大塚です。
今回は、CS実践者インタビューということで、日本でただ一人「カスタマーサポート エバンジェリスト」として活動している藤本大輔さん(現在はコードキャンプ株式会社でCSを担当しながらカラクリ株式会社のCS顧問を務める)と共に、株式会社スペースマーケットのカスタマーサクセス部マネージャー西村高史さんにお話を伺ってきました。
スペースマーケットは、シェアリングエコノミーの考え方をベースにスペースを貸したいホストと、スペースを利用したいゲストを繋ぐマッチングサイトを運営している会社です。約8,000ものユニークなスペースの予約から支払いまでワンストップで簡単に行えるサービスになっています。そのため、C to Cのやり取りが発生します。
C to Cにおいては、サービス利用の継続のためにサポートが非常に重要になってきます。CSに力を入れる会社の価値観に加え、西村さんのCSへの熱い想いが次々と価値を生み出してきました。
チームとしてCSメンバーを育成するにはどうすれば良いのか?CSの役割が不満を吸い上げるだけではないとはどういう意味か?今後どのようなCSが求められるのか?
といったことを語ってもらいました。話の中から、根本には西村さんのCSへの熱い気持ちがあることを強く感じるインタビューになっています。
 株式会社スペースマーケット カスタマーサクセス部 西村 高史
株式会社スペースマーケット カスタマーサクセス部 西村 高史
1977年 北海道生まれ。7年間のエンジニア経験の後、CSの業界に身を置き10年間従事。ISP、外資系のコンピューターメーカーでのサポート業務を経て、Amazonの出品者サポートを行うチームでマネジメントの経験を積む。
現在は、株式会社スペースマーケットのカスタマーサクセス部マネージャーとしてCSの対応や運営に関わる全てに携わっている。
CSを通してカスタマーの人生をサポートする

大塚
本日はよろしくお願いします。
まず、西村さんがスペースマーケットに入った経緯を教えてください。
西村
大きく分けて2つあります。1つは元同僚がスペースマーケットに務めており、スペースマーケットのことを色々話してくれていたのがきっかけです。興味を持ったのは、今までにないシェアリングエコノミーに属していること。そして、これからビジネスの形態は個人同士でのサービスのやり取りが増えていく中で、そこをCSとしてサポートするということは個人個人の人生をサポートすることであることに魅力を感じた。というのが理由です。
藤本
前にも、僕の会社で熱く語ってくれましたよね。
大塚
「人生をサポートする」というのはもう少し詳しく言うと、どういうことでしょうか?
西村
これまでCSに求められていたのは、企業のサービスを利用する上で起きた問題を解決することなので、どちらかというと受け身の仕事だと思います。ただ、個人間でのC to Cのやり取りになると、サービスを利用する背景もパーソナルなものになってきます。そのパーソナルな部分の問題を解決することができるという意味で、よりその人に密接したサポートになると思います。
スペースマーケット自体はB to Cと捉えられることもあるのですが、プラットフォームで見るとC to C だと考えています。法人の方の利用もありますが、個人間のやり取りもできるということを前提に作られていますので、そういった意味でC to Cです。
藤本
僕が事業会社のCSに移ったのは、クライアントワークでは限界があるなと感じた側面があるのですが、西村さんはそういったことはありましたか?
西村
私も10年くらいCSの仕事をアウトソースとインハウス両方でやったのですが、自分の経験上アウトソースとインハウスで得られたものは異なります。アウトソースにおいては数字、データを分析して生産性を高めるということが勉強になりました。
その反面、サービスのカルチャーの醸成や利用者へのエジュケーションはインハウスでないとできないと思います。
それぞれに良さはあると思いますが、自分の中ではインハウスでやることが重要だなと思います。
CSメンバーには行動を通して信条を伝える

藤本
今スペースマーケットのCSメンバーは何名いるんですか?
西村
私を入れて6名ですね。
藤本
メンバーの方はCS未経験の方が多いと伺っています。未経験の方が多いとカルチャーの醸成が難しいと思うのですが、新規のCSメンバーに対して何か工夫されていることはありますか?
西村
スペースマーケットにはミッションとバリューがあり、CSの中にtenets(信条)という10の信条があるので、それに則って行動します。でもメンバーに浸透させるには、ただ言葉を覚えてもらうのではなく、マネージャーの行動が重要だと思います。マネージャーがメンバーから相談を受けた時はtenets(信条)に則ったアドバイスをします。
大塚
10の信条のうち、例えば最近メンバーに話したものは何ですか?
西村
tenets(信条)の一つに、「私たちのカスタマーはホストとゲスト」というものがあります。メンバーから対応の相談を受けた時、本質的な質問は「会社が損しないようにするにはどうすれば良いか」といった内容だったので、「なぜ今の話の中にカスタマーがいないの?」と聞き返しました。
もちろん会社の利益を守ることも重要です。ただ、それ以上に、私たちはカスタマーのことを考えて行動しなければならないと思っています。本質的な問題で、忘れがちになりやすいものなので、フィードバックをする時には必ずtenets(信条)に沿うようにしています。
あと、CSのオペレーションを見直すミーティングで、時間を短縮するためにカスタマーとのやり取りを省略するという話に対して「それは、カスタマーのためにならないならやらない、それで時間がかかるなら目標を見直すようにしましょう。」といった形で、話の中にカスタマーが出てくるように意識しています。
大塚
こういった信条があるのはCS部門においては、一般的なんですか?
藤本
コールセンターの朝会等では、だいたいモットーを唱和します。10もの行動指針があるのはあまり聞きませんね。フィードバックするにしてもフィードバックする側が気づかないといけないので、西村さん自身の中にちゃんとそういった信条が浸透しているのでしょうね。
西村
行動指針という形で自分たちが迷った時に、tenets(信条)を基準に解答を導き出せるようにしています。マネージャーである自分が判断基準ではなく、行動指針を基準に判断します。
CSを含む部門間のやり取りがサービスを強化する

藤本
スペースマーケットがCSにおいてホスピタリティーを大切にしていることが伝わってきたのですが、生産性の部分で工夫しておられることはありますか?
西村
よくあるKPI、顧客満足度、初回返答時間、ファースト・レゾリューション・タイム(初回解決時間)、1回で完結出来たか、平均対応時間といったものはあります。これらはオペレーションの正常性を測る指標として持っています。「カスタマーを待たせていないかどうか」をそういった数字を元に判断しています。
藤本
スペースマーケットさんを利用すると、よくレビューの案内が来るのですが、お客様からの意見を反映させるためにどういった取り組みをされていますか?
西村
物理的な距離もそうですが、各部門の隔たりがなく関係性としての距離が近いので、エンジニア・デザイナーの人と情報を共有するための仕組みはすでに出来上がっています。アンケートのコメントは随時共有し、必要に応じてそれを一つ一つ解決していくという感じですね。地道なやり方でやっています。
藤本
情報共有や部門の距離の近さというのは、成長している企業には共通だなというのは感じます。企業によっては、CS部門に対して情報が届くことが遅いことがありますからね。
西村
そうですね。過去にいた会社では「今日ローンチしました。」みたいなこともありましたね。自社のサービスなのにプレスリリースで存在を知るみたいな(笑)
CSの役割は不満を聞くだけでなくサービスの価値を正しく伝えること

大塚
CSが他部門と情報を共有することを大切にしておられるのはなぜですか?
西村
そうですね。「共有しない」という発想がないというか…よくCSの情報共有というと「どうやってお客様の不満を共有しているのですか?」といったことを聞かれるのですが、実は明確に不満を伝えられるカスタマーというのは、ほとんどおられず、全体の0.0…%なんです。
なので、実際の不満の声に合わせてサービスの軸をぶらすのではなく、不満を感じているお客様がいることを理解したうえで、商品の機能やメリットを伝えていくことを大切にしています。
もちろん直すべきところはありますが、エンジニアやデザイナーが必死になって考えてくれた、サービスや世界観もしっかり伝えた上で、プラットフォームを使ってもらって成功体験をして欲しいと考えています。なので、CSとして不満を吸い出すだけでなく、機能の意図や価値をしっかり伝えることを大切にしています。
大塚
セールスやマーケティングで行うようなことを意識されているのですね。
西村
そうですね。CSもセールスもマーケティングも徐々に垣根がなくなっていくと思います。
藤本
CSというとメール応対というイメージがありますが、カスタマーとコミュニケーションを取ることに重点がシフトしてくような気がします。
多様性がスペースマーケットのCSの「正しさ」を作っていく

大塚
そうなると、CSがいろんなところをカバーしているので、CSの成果が見えにくいのかなと思ったのですが、その辺りはいかがでしょうか?
西村
特別な取り組みはしていないですね。CSにおいての顧客満足度ってサービスへの満足度なのか、対応への満足度なのかわからないので意味がないんですよね。だから報告会でもそういった数字はあまり共有しません。その代わりに、カスタマーの問い合わせのトレンドやCSが取り組んでいることをアウトプットしています。
会社がCSに求めるのは、カスタマーの声を届けることと、働いているメンバーの取り組みなので、数字だけが重要なわけではないんです。
数値の部分で成果を図る生産性至上主義はアウトソースの会社のやり方だと思います。
そこを主軸にしてしまうと「何が大切なのか」を見失いがちになると思います。とはいえ、生産性を無視できないので、そこはしっかりと担保した上で動いていきます。
また、CSの仕事というと、クレームなどの問題を解決する仕事で、マイナスをゼロにするという認識が強いです。もちろんそういった仕事も大切なのですが、それだけだとどうしてもモチベーションが上がらないですよね。なので、「いかに会社のためになることをやっていくのか」といった視点が大切だと思います。
藤本
CSの経験者であればあるほど、数字で動くかもしれませんね。逆に未経験者を採用するようにしてたりするのでしょうか?
西村
そうですね。未経験者を採用するようにしています。僕自身が元々CSをやっていたことがあり、自分の中である程度の「正しさ」ができていると思います。でもそれが、スペースマーケットのカスタマーにとっての「正しさ」かどうかはわからない。なので、価値観や考えが偏らないように、いろんな「正しさ」を取り入れたいと思い、未経験者を採用するようにしています。
様々な「正しさ」を持つメンバーが集まって、スペースマーケットのCSにおいての「正しさ」を作っていきたいと考えています。未経験者を取るのは大変な面もあるのですが、これからカルチャーを作っていく時期だからこそ、大変でも妥協せずにやっていきます。
藤本
確かに一度文化ができると、それを変えるのは難しいですよね。
西村
はい、ここからさき事業がスケールしていく上で、サービスの信頼を担保するCSも柔軟性のあるカルチャーを作っていく必要を感じています。
目標管理をメンバーに任せることで責任感を育む

藤本
画一的でない分、何か仕事の教え方などで工夫していることはありますか?
西村
そもそも僕は、コールセンターのような組織構造があまり好きではないんです。明確な理由は言えない面もあるのですが(笑)なので、誰かをリーダーにするのではなく、メンバー全員がリーダーであり、役割をローテーションしていきたいと考えています。
だから、KPIの管理もマネージャーではなくメンバーが行うようにしています。前提としてメンバー全員が自分の対応だけでなく、全体を見れるようになってほしいと考えています。
CSはどうしてもスタンドプレーになりがちですが、自分達のやったことがどう会社に影響するのか、自分達は会社のどのポジションにいるのかといった広い視点を持って欲しいと考えています。そのためにKPIを自分達で管理することで自分達の仕事に責任を持ってもらいたいです。
藤本
任せるといっても大変ですよね?
西村
そうですね。裏ではちゃんと見てますから(笑)
大塚
コントロールではなくエンパワーする感じですね。
西村
はい、一緒に進んでいく感じですね。
まとめ
これからビジネス形態は個人同士でのサービスのやり取りが増えていく中で、CSとしてサポートするということは個人の人生をサポートすることであると語ってくれた西村氏。
サービスのカルチャーの醸成や利用者へのエジュケーションはインハウスでないと難しいと話をする中で、スペースマーケットにはCSの中にtensetsに則ったアドバイスをしています。
行動指針という形で迷った時にtesetsを基準に解答を導き出せるようにしているのも、CS部門の生産性を測る指標においても、全てはカスタマーのためという想いが伝わってきました。
後半の記事では、CSが自身の天職だと語るCSへの想いや、CSに求められること。CS成功の秘訣。スペースマーケットのCSがスタンダードになるためのご自身の取り組みなどをお話して頂きますので、続けてご覧ください。
■大塚 真吾
プロサッカークラブのマネジメント職を経験後、ダイレクトマーケティング支援の株式会社ファインドスターに入社。サブスクリプション型の通販のマーケティングを100社以上支援。2013年、スタークス株式会社に入社し、2016年取締役に就任。現在、クラウド型の物流プラットフォーム「クラウドロジ」とLINE@に特化したCSツール「CScloud」を提供。
■藤本 大輔
1982年 福岡生まれ。テレマーケティング会社で電話営業を経験の後、コンタクトセンター運営会社に移り約10年間大手インターネットサービスプロバイダのコールセンターマネジメントに従事。その後、大手ソーシャルゲーム会社のCSを経て、フリマアプリ運営会社のCSグループマネージャーとしてチャットサポートの導入やCSイベントの開催を主導。現在はコードキャンプ株式会社のCSチームを率いる。本業の他に日本で唯一の「カスタマーサポート エバンジェリスト」として、コンサルタントやCSイベントの企画などで活動中。キャッチコピーは“CSに狂っている男”。